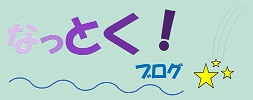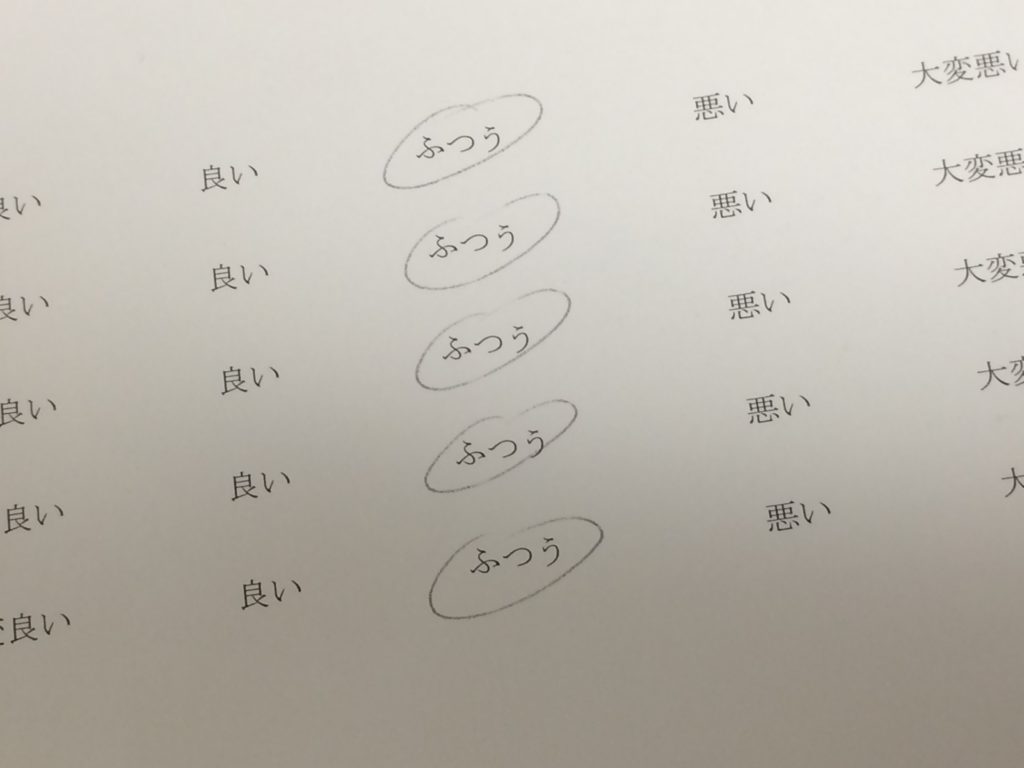
日本に住んでいると、日本人が取る行動が当たり前だと思ってしまうものです。
しかし、そんな行動も、外国人から見れば奇怪に思えることが多々あります。
まあまあと言う表現
そんな行動の1つに、「まあまあ」というような、あやふやな表現をすることがあげられます。
「あのお店の料理は美味しかった?」
との問いに、
「そうですね。まあまあですね。」
と答えると、日本人同士なら、普通の会話という感じです。
しかし、外国人から見れば、
「いったい、美味しいのか、美味しくないのか、どっちなのか!」
とイライラしたりするものです。
日本人の曖昧さは外国人には奇怪に映る
私は学生時代に数か月間、海外に滞在していた経験や、就職後もプライベートで海外に十数回行った経緯から、国際交流の場があると興味を持って積極的に参加します。
すると、日本人の曖昧さに対して、外国人が怪訝な顔をする場面に、出くわすことが非常に多くあります。
先日も、日本に滞在するある外国人が、近くにある美容院の評判が知りたくて、2人の日本人女性に聞いてみたところ、
「悪くはないけど、良くもない」、「まあまあだね」
というような言い方をされ、それを聞いたその外国人は
「いったいどっちなの?」
と少し呆れていた感じでした。
外国人から見れば、
「悪くない」=「良い」
「良くない」=「悪い」
という感覚があるので、「悪くない」けど「良くない」とはいったいどういうこと?となるわけですね。同様に、
YESの反対はNO
NOの反対はYES
ですが、これが日本人になると、「YESではないけどNOでもない」という表現があったりするわけで、外国人から見れば、まさに奇怪です。
アンケートにも曖昧さが表れる
こういった感覚の違いは、アンケートの表現なんかに表れています。
例えば、アンケートの選択回答欄にある選択肢には、
良い 悪い ふつう
或いは
低い 高い どちらでもない
といった中間的な表現(ふつう、どちらでもない)が当たり前のようにあります。海外だとこれは、
良い 悪い わからない
というようになるでしょう。
日本特有の傾向
さて、そもそも、まあまあという言葉の意味はなんでしょう。
辞書を調べてみると「十分ではないが、一応 満足できる」というかんじで載ってました。
では、このような表現の言葉は外国語にはないのかというと、そうではなくて、たいていの言語でもあります。
例えば英語だと「so-so」なんて表現がそれに当たりますね。
しかし、言葉としては存在しても、実際の日常会話ではあまり使われないようです。
「まあまあ」とか「どっちでもいい」といったあいまいな表現をするのは、日本人特有の傾向です。
恐らくそれは、和を重んじたり、相手をいたわったり、おもてなしの心を持ったりする、日本人の優しさから来ているのではないかと思います。
つまり、物事は白黒結論づける必要はない訳ですし、いたずらに反発を買うような意見を言うよりも、相手と歩調を合わせて行った方が良い、という姿勢から来ているのではないでしょうか。
あいまいな表現は、日本人にしてみれば、ごくごく普通で当たり前の言葉だったりしますが、ともすれば、外国人にとっては、単に、主張や意見、信念、信条がなく中身のない人、優柔不断な人だと映るかも知れません。
海外の人と接する時は、「まあまあ」や「どっちでもいい」というあいまいな表現は控え、自分の意見や主張をはっきりと伝えて、誤解のないコミュニケーションを取って行きたいですね。