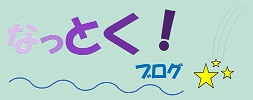将棋の駒の飛車が成ると竜王になりますが、これは龍王とも書きます。
しかし、古代の生物である恐竜は恐龍と書くことはありません。

龍と竜は何が違うのか?
本来は同じ字なので、恐竜と恐龍の両方の書き方があってもよさそうですが、実際には恐竜だけしか用いられません。
気になった私は調べてみることにしました。
竜と龍
竜と龍は字体が異なるだけで、「りゅう」または「たつ」と読み、共に大蛇のような想像上の生物のことを意味します。
竜は常用漢字ですが、龍は常用漢字外で、旧字に相当します。
従って、常用漢字外で旧字でもある龍は使わずに、竜を使うようにするのが本来あるべき使用方法と言えます。
しかし、実際は龍という漢字は頻繁に使われています。
幾つか例をあげてみると、龍神、龍宮、龍馬、龍王などたくさんあります。
しかし、これらの4例は、いずれも竜神、竜宮、竜馬、竜王とも書き、どちらの字も使うことができます。
また、竜と龍は地名や人名などの固有名詞でも広く用いられ、両方の漢字が併用される場合もあれば、区別して使われることもあります。
なぜ恐龍ではないか
では、恐竜の場合はどうでしょう。恐龍という熟語は、ほとんど見たことがありませんし、字としても馴染みません。
実際に、IMEの漢字変換で確かめたところ、上記にあげた4例の熟語の場合は、いずれも変換候補として、龍を使う場合と竜を使う場合の両方が出てきました。
しかし、恐竜については変換候補として、恐竜しか出てこず、恐龍が不適切であることが表れています。
なぜ恐龍とは言わないのかを考察すると、言葉の誕生が割と新しいからだと考えられます。
例えば、龍神、龍宮、龍馬、龍王と言った言葉はその歴史が長く、新字である竜が正式に定められる前から使われていました。
龍宮(竜宮)や龍神(竜神)は、中国古来から伝わる伝説上のものですから、もともと旧字である龍が使われていました。(そもそも、中国では竜という字は非公式な字です)
将棋の駒の名前でもある龍馬や龍王は、日本への将棋の伝来が8世紀以前、発見された龍の名前が付く駒は13世紀以前のものだと言われていますから、旧字である龍が使われていました。
しかし、恐竜が科学的に認識されて恐竜という呼び方がされたのは世界的に見ても19世紀以降ですから、旧字としての龍はふさわしくなかったと言えます。
つまり、上記の4例のように旧字に相当する龍が、新字である竜と書かれるようになったのは時代の流れで自然と変化して来たことですから、名残として龍の書き方が残っているのです。
しかし、新字として竜という漢字が定着した後に生まれた熟語の場合は、旧字である龍が使われるのは不適切なことですから、自ずと恐竜と命名されたと考えるべきでしょう。
あわせて読みたい「竜とドラゴン」訳は同じだが実は全く正反対の生き物!違いはここ!
恐竜の発見は近年
さて、ここまで説明した内容は、あくまで憶測の域を超えませんから、実際に詳しく調べてみました。その結果、大筋で正しかったことが分かりました。
さっそく、恐竜の発見から今日に至るまでの歴史と、漢字の移り変わりの流れを見てみましょう。
そもそも、英国の古生物学者であるリチャード・オーウェン氏が、恐竜という新しい生物のグループに初めて名前(=DINOSAURIA)を付けたのは1842年のことでした。
これを初めて日本語に訳したのは、東京大学教授で、古生物学者でもあった横山又二郎氏(1860~1942年)です。
これは横山氏が1895年に著した「化石学教科書(中巻)」に記載されたものですが、実はこの時の訳では、あくまで「恐龍」でした。
この経緯については、福井県立恐竜博物館のサイト中(https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/dino/faq/r02005.html)に詳しく書かれていますので参考にして下さい。
横山又二郎氏は、古生物学の研究の道を開いた方で、始祖鳥などの和訳も果たし、その後の日本の古生物学に大きく影響を与えています。
要は、日本で恐竜のもととなる恐龍という言葉が初めて生まれたのは、上記の書物が発行された時(1895年)なのですね。
しかし、この頃は未だ日本国内で恐竜の化石が発見されることはなかったため、恐龍という言葉は、あくまで古生物学の学術語として留まっていたと言えます。
日本で最初に恐竜の化石が発見されたのは、1978年(岩手県)のことですから、恐龍という言葉が誕生してから80年以上も経過しています。
恐竜の卵の化石の発見については、それよりも早くて1965年(山口県)とのことですが、それでも恐龍という言葉が誕生してから70年が経過しています。
非公式には1930年代に恐竜の発掘が日本であったという話もありますが、それでも初めて恐龍と和訳されてから40年近くが経過しています。
つまり、最初に恐龍という言葉が生まれてから、長い期間、単なる学術語として使われるだけで、広く一般に使われる言葉ではなかったと言えるのです。
そして、日本で初めて恐竜の化石が発見されてから各地で発掘が進んでいったのは、最初の化石が発見された1978年以降のことで、そこから1990年代の恐竜ブームにつながっています。
龍と竜の違いは歴史的な流れを見ると分かる
ここで問題なのは、なぜ最初に訳された「恐龍」が定着せず、「恐竜」が定着したかです。
では、龍と竜の2つの漢字の歴史的な流れを見てみましょう。
実は、龍も竜も、日本の漢字の歴史の中では両方とも存在していて、長い間2つとも使われてきていました。両者とも異体字ということで併用されていたのです。
1919年(大正8年)の、漢字について実質上初めて公式な動きがあった漢字整理案(文部省)では、龍も竜も一般に使用する漢字として扱われています。
但し、ここでは龍が正式な字で、竜はあくまで許容される字(許容體案)として扱われていました。
その後、1923年(大正12年)には常用漢字表(臨時国語調査会)が制定されました。(のちの1981年に制定された常用漢字表とは別なもの)
そこでは、漢字を制限する動きがあったものの、関東大震災の影響で事実上は実現しませんでしたが、ここでは龍がその漢字表に出ていました。
1942年(昭和17年)には、標準漢字表(国語審議会)が定められました。この時、常用漢字ではなく準常用漢字としてでしたが、「龍(竜)」という記述がされています。要するに、龍が主、竜は従だったのです。
1946年(昭和23年)には、当用漢字表が定められましたが、この時は、龍も竜もどちらも当用漢字の対象外となっています。
しかし、この中で定められた水部(さんずい)の漢字には、「滝(瀧)」という定めがあり、龍よりも竜を主にしようとする傾向がうかがわれます。
1951年(昭和26年)には、固有名詞の使用上で不便があった背景から、人名用漢字別表(法務省)が定められて、この中に龍が含まれました。
その3年後の1954年(昭和29年)には、既に定められていた当用漢字を補足する目的で当用漢字補正資料(文部省)が発行され、この時に竜が追加で定められました。
1978年(昭和53年)に定められたJIS第1水準漢字表(通産省)では、龍と竜の両方が定められました。
そして、その3年後の1981年(昭和56年)に定められた常用漢字表(文部省)では、竜(龍) と記述されて竜が主、龍は従という関係が明確になりました。同年、人名用とされていた龍は、人名用に許可されるという位置づけになっています。
このように、お互い異体字である「龍」と「竜」は、近年の歴史の中でも、どちらに統一しようかと揺れ動いていました。
しかし、おおむねその流れを見れば、戦前はほぼ「龍」が主、戦後は揺れ動きながら「竜」にシフトして行く流れが起き、1981年に明確に「竜」が主となっています。
そして、龍から竜に移行していった分岐点は、共に当用漢字から外されていた時に、竜のみが追加で定められた1954年(当用漢字補正資料)と言えます。
ちなみに、漢字の歴史については、国立国会図書館のリサーチナビ(https://rnavi.ndl.go.jp/jp/guides/post_576.html#2-1)を利用すると便利です。
今まで説明してきた、龍と竜の漢字の流れを簡単に表にまとめておきます。
| 年 | 事柄 | 龍 | 竜 | 備考 |
| 1919(T08) | 漢字整理案 | 龍 | (竜) | 竜は許容 |
| 1923(T12) | 常用漢字表 | 龍 | ― | |
| 1942(S17) | 標準漢字表 | 龍 | (竜) | 準常用として龍(竜)と制定 |
| 1946(S21) | 当用漢字表 | ― | ― | 龍も竜も対象外 |
| 1951(S26) | 人名用漢字別表 | 龍 | ― | 人名用に龍を追加 |
| 1954(S29) | 当用漢字補正資料 | ― | 竜 | 竜を当用漢字に追加 |
| 1978(S53) | JIS第1水準漢字表 | 龍 | 竜 | 龍も竜も制定 |
| 1981(S56) | 常用漢字表 | (龍) | 竜 | 竜(龍)と制定 |
| 1981(S56) | 人名用漢字許容字体表 | (龍) | 龍が許容という位置付けに |
恐龍から恐竜へ
以上、、恐竜の化石発見の歴史と、龍と竜の漢字の歴史に触れてきましたが、両者を突き合わせてみましょう。
初めて、恐龍と和訳された1895年は、まだ公式に漢字の使い方を定める背景はありませんでした。
しかし、1919年の漢字整理案で、龍が正式な字(竜は許容される字)とされていたことから、龍を主とする傾向が恐龍と和訳された背景にあったと考えられます。
つまり、最初に「恐龍」と和訳したのは自然な流れだったと言えるのですね。
日本において実質上、初めて恐竜の化石が発掘されたのは1978年ですから、それまでは恐龍は学術語としての意味だけで、一般的には広まっていなかったと言えます。
1978年と言えば、当用漢字に竜はあるものの、龍はない時代ですから、この発掘を機に一般に広まって行ったと考えると、龍ではなく竜が(「恐龍」ではなく「恐竜」が)使われて行くのも当然です。
そして、3年後の1981年に常用漢字表が定められて、竜が主、龍は従という関係がいよいよ明確になり、竜を使う方向に大きく動いていくことになります。
最初の発掘ののち、恐竜化石の発掘はどんどん進み、その後の90年代の本格的な恐竜ブームにつながっています。
このように、恐竜が学術用語としてではなく一般名称として使われる言葉として広まっていった時代は、既に竜が主で、龍は従であったことになります。
つまり、龍と竜の位置づけの変化の過程で、当初「恐龍」と訳されていたものが、自然な流れで「恐竜」に定着して行ったのです。
竜と龍ってけっこう深いですね。
ドラゴンは龍か竜か
ところで、西洋のドラゴンは龍なのか竜なのかという議論があります。
よく言われているのが、”東洋の龍(竜)は龍と書き、西洋のドラゴンは竜と書いて使い分ける”という話です。
これについて、結論をひと言でいえば、
「竜も龍も異体字で龍は竜の旧字なので漢字の上で区別すべきではない」
です。
但し、実際には西洋のドラゴンを竜、東洋の龍(竜)を龍のように使い分ける傾向があるのも事実です。
一部、慣習にもなっている面もありますが、あくまで漢字としての使い分けはありません。
使い分ける傾向や慣習が残っているのは、恐竜を恐龍と書かないこととも少し関係があります。
東洋の龍(竜)も、西洋のドラゴンも本来は全く別な生き物ですが、相互に訳の対象となっています。竜(龍)を英訳すればdragon(ドラゴン)、dragonを和訳すれば竜(龍)です。
両者には架空の生き物という共通点がありますから、フィクションの世界にしか登場しません。
フィクションである映画や物語などが、西洋と東洋の間で相互に訳されるようになったのは、近年においてが最も盛んと言えます。
つまり、龍ではなく竜という漢字が定着して以降の訳数が圧倒的に多いのです。
また、西洋で初めて恐竜の化石が発見されてから、一部で「ドラゴンは実在したのでは」と思われたこともありました。
そんなことから、ドラゴンと恐竜を結び付けようとする動きも少しあったのですね。
それに加えて、龍の起源である中国では、竜という漢字は使われず、龍という漢字(現在では簡体字の「龙)のみが使われて来ました。(中国では、竜は非公式な漢字)
従って、中国では、東洋の龍(竜)は当然「龍」と表現されるわけです。だから日本では、ドラゴンを「竜」と表現すれば、東洋の龍と西洋のドラゴンを区別しやすいという背景があったと言えます。
このように、「ドラゴンは竜」という傾向が根付いたのは、恐龍ではなく恐竜と表現する背景と同様の歴史的な流れに加え、中国で使われる漢字の影響もあったと言えるでしょう。
つまり、「ドラゴンは竜」と決めたと言うよりも、「ドラゴンは竜」というイメージが自然な形で定着して行ったと言うべきでしょう。
あわせて読みたい「竜とドラゴン」訳は同じだが実は全く正反対の生き物!違いはここ!
こんな字もある
さて、龍や竜の部位を含む漢字は他にもあります。例えば、「瀧と滝」や「籠と篭」がそうです。
瀧や滝は字体が異なるだけで、「たき」と読み、共に高いところからほぼ垂直に流れ落ちる水、急流のことを意味します。
滝は常用漢字ですが、瀧は常用漢字外で旧字に当たります。
従って、滝の方を用いるのが通常ですが、滝沢と瀧沢のように固有名詞で用いられる場合などでは区別されています。
一方、籠や篭は、「かご」や「ろう」と読み、共に竹などで編んで作った入れ物を意味します。
籠が標準的な字で、篭は異体字に相当します。異体字とは、「煙」に対する「烟」などのように、意味や発音が同じで通用する漢字のことです。
テニスを庭球と呼ぶように、バスケットボールのことを籠球(ろうきゅう)と呼びますが、篭球という言葉はあっても一般的ではなく殆ど使われていません。
これは、龍や瀧がそれぞれ竜や滝の旧字であるのに対して、籠は篭の旧字では無く、籠が標準的な字で、篭は異体字であることが影響しているのでしょう。
日常なにげなく使っている漢字も、掘り下げてみると興味深いものがありますね。
あわせて読みたい「天地無用」って意味を間違えたら困るけど、とても間違いやすい。